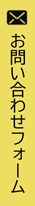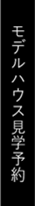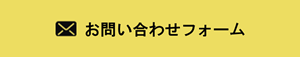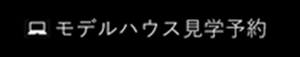お知らせ・ブログinformation
2025.09.01
注文住宅をローコストで建てる際のデメリットとは?注意点も解説

「注文住宅を建てたいけれど、予算が限られている」「ローコスト住宅って実際どうなのだろう」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ローコスト住宅は、一般的な注文住宅よりも建築コストを抑えられるのが魅力です。その一方で、「間取りの自由度が低い」「メンテナンス費用がかさむ」「資産価値が下がりやすい」など、大きくわけて5つのデメリットがあります。
そこで今回は、ローコスト住宅の購入前に知っておきたいデメリットと、後悔を防ぐための対策を徹底解説します。
ローコストな注文住宅とは?価格帯と安さの仕組み

ローコスト住宅とは、坪単価30万〜50万円程度で建築できる住宅のことです。
一般的な注文住宅よりも予算を抑えやすいため、近年は20代・30代の若い世代を中心に、幅広いファミリー層から支持されています。
まずは、ローコスト住宅の基本的な定義と、低価格を実現する仕組みを見ていきましょう。
一般的な注文住宅との価格比較
| 項目 | 大手ハウスメーカー | ローコスト住宅メーカー |
| 坪単価の目安 | 80万〜120万円 | 30万〜50万円 |
| 35坪の建築費 | 2,800万〜4,200万円 | 1,050万〜1,750万円 |
住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」によると、一般的な注文住宅の坪単価はおよそ110万円とされています。この坪単価で35坪の家を建てると、およそ3,850万円が必要です。
一方、ローコスト住宅の平均坪単価は30万〜50万円であるため、35坪の住まいの場合は、1,050万〜1,750万円程度で建てられます。同じ広さでも最大2,000万円以上の価格差があることから、コストパフォーマンスを重視する方にとって、ローコスト住宅は魅力的に感じられるでしょう。
出典:住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」
ローコスト住宅の安さの理由
ローコスト住宅の販売価格は、材料費・人件費・広告費を抑える仕組みによって実現されています。具体的には、次のような工夫があります。
- 建材を大量一括購入し、仕入れコストを削減
- 間取り・仕様を規格化し、設計の手間と工期を短縮
- 施工スタッフを効率的に配置し、人件費を削減
- 展示場やモデルハウスを最小限にし、広告宣伝費を削減
このように、家づくりのプロセスを簡素化し、無駄なコストを徹底的に省くことで、坪単価30万〜50万円という価格帯を実現しているのです。
2025年4月の建築基準法改正とローコスト住宅への影響
2025年4月から建築のルールが大きく変わり、家を建てるときに守る基準が厳しくなりました。これは安全性や省エネを重視する流れの中で行われた改正で、2050年カーボンニュートラルの政策目標とも関係しています。
その結果、「安さ」を売りにしたローコスト住宅は、従来の仕様のままでは建てにくい状況になっています。以下、建築基準法改正によるローコスト住宅への影響をご説明します。
※以下、国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」などを参照してまとめています。
四号特例が縮小され、チェックが厳しくなった
これまでは「小さな木造の家は細かい審査を省いてよい」というルール(四号特例)がありましたが、改正後はこの特例が大きく縮小され、2階建てでも細かい構造のチェックが必要となりました。つまり、柱や壁の配置、基礎の設計などを、役所・検査機関に、しっかりと確認してもらわなければならなくなったのです。
すべての新築で省エネ基準が必須に
新築住宅はすべて「省エネ基準」のクリアが義務化され、外壁や窓の断熱性能、エアコンや給湯器などの効率までチェックされます。これまでの標準仕様では基準に届かず、断熱材を厚くしたり、高性能な窓や設備に変更したりする必要が出てきました。
構造計算が必要なケースが増加
改正後は、これまで簡単な計算で済んでいた家でも、より詳しい「構造計算」が必要となりました。専門家による計算や追加資料の提出が求められるため、設計の手間とコストがかかり、その分が住宅価格に上乗せされる可能性があります。
ローコスト住宅への影響
これらの改正の結果、さまざまな追加費用が発生しやすくなり、従来のように「低価格」を前面に出した家づくりは難しくなりました。たとえば、断熱材を厚くする工事や高性能サッシ・高効率給湯器の導入など、これまでオプション扱いだった仕様が必須に近づいています。
そのため、ローコスト住宅は以前ほど現実的な選択肢ではなくなったといえるでしょう。
ローコストな注文住宅|5つのデメリットと対策
本体価格が魅力のローコスト住宅ですが、安さだけを理由に選んでしまうと、住み始めてから思わぬ後悔を招くリスクがあります。
購入後に「やっぱり失敗だった」とならないためには、以下5つのデメリットをしっかり理解し、適切な対策を講じることが大切です。
デメリット①「間取り・デザインの自由度が低い」
ローコスト住宅では、コスト削減のために規格化されたプランを採用することが多く、間取りやデザインの自由度が大きく制限されます。たとえば、建物の形状は施工効率を優先した箱型が軸となるため、個性的な外観や複雑な間取りの実現は難しいでしょう。
また、使用される建材や設備は、大量一括仕入れによる標準仕様に限定されるため、選べるグレードや種類が限られます。結果として「もっと自由に設計できると思っていたのに……」と感じるケースは少なくありません。
デメリット②「住宅性能(断熱・耐震)に不安が残る」
ローコスト住宅は建築基準法を満たす最低限の安全性は確保されていますが、断熱性・耐震性は、高性能な注文住宅に比べて劣る傾向があります。
断熱性能が低いと冷暖房効率が悪くなり、長期的に見ると光熱費がかさみます。省エネ基準ぎりぎりの仕様では、夏は蒸し暑く、冬は底冷えするような住環境になりがちです。
また、ほとんどのローコスト住宅は、建築基準法で定められた耐震等級2を満たしており、一定の耐震性は確保されています。より安全性を高めたいなら、等級3などのプランを選びたいところですが、その場合はオプション扱いとなり、追加費用が発生します。
デメリット③「メンテナンス費用が高くなりやすい」
ローコスト住宅は、コスト削減のために安価な建材を使うケースが一般的です。こうした建材は劣化が早く、結果的にメンテナンスの頻度が増えます。初期費用を抑えたつもりでも、長期的に見ると総コストが高くなるリスクがあるのです。
たとえば、外壁塗装は10~15年ごとに必要となり、その都度100万~150万円ほどの費用が発生します。屋根の補修も15~20年周期で50万~100万円程度、さらにキッチンや浴室などの水回り設備の交換には、それ以上にまとまった費用が必要です。
短期的には安く見えても、将来の維持費まで含めて考えると、結果的に割高になる可能性がある点に注意しましょう。
デメリット④「オプション費用で結果的に割高になる」
ローコスト住宅の標準仕様は必要最低限に設定されているため、希望する間取りや設備を実現しようとすると、オプション費用がかさみます。
具体例を挙げると、キッチンのグレードアップに数十万円、こだわりの床材・外壁材への変更では数十万~百万円以上の追加費用が発生することも珍しくありません。こうしたオプションを積み重ねると、最終的には一般的な注文住宅と変わらない金額になってしまいます。
デメリット⑤「資産価値の低下リスク」
ローコスト住宅は、建材の質やブランド力の影響から、将来的な資産価値が下がる傾向にあります。
安価な建材や画一的なデザインは、築年数が浅くても「古びた印象」を与えやすく、不動産市場での評価を下げる要因です。さらに、大手ハウスメーカーとのブランド力の差も、売却時の査定額に影響することが少なくありません。
将来的に売却・賃貸を考えているなら、初期費用だけでなく、資産価値の維持も踏まえた選択が重要となります。
【要注意】ローコストな注文住宅をおすすめしない人の特徴
ローコスト住宅は、コストを抑えた家づくりができる反面、自由度や性能面に制約があるため、すべての人に向いているわけではありません。ここでは、ローコスト住宅をおすすめしない人の特徴をご紹介します。
こだわりの間取りを実現したい人
特定の動線や部屋の配置にこだわる場合、標準プランでは対応できないことが多く、カスタマイズには追加費用が発生します。
そもそもローコスト住宅は、建物の形状や仕様をシンプルにすることで工事の効率を高め、コストを抑えている住宅商品です。その分、間取りやデザインの自由度は限られており、オリジナル性を重視する方には、不向きといえるでしょう。
高い住宅性能を求める人
標準仕様の場合、断熱性や耐震性、省エネ性能などが、ハイグレードな住宅と比較すると見劣りすることがあります。もちろんオプションで住宅性能を高めることはできますが、その分の追加費用がかかり、最終的には一般的な注文住宅と変わらないコストになります。
住宅性能を重視するなら、初期費用だけでなく、将来の快適性やランニングコストまで含めて検討することをおすすめします。
メンテナンスフリーの注文住宅はある?
一般的な注文住宅は、外壁や屋根の塗り替え、コーキングの打ち替えなど、定期的なメンテナンスが必要です。特にローコスト住宅では安価な建材が使われることが多く、劣化が早まり、メンテナンス費用がかさむ傾向があります。
しかし近年は、こうした将来的なメンテナンス負担を大幅に減らす建材・工法が注目されています。設計段階から経年変化によるトラブルが起こりにくい住まいづくりを提案する工務店も増えており、長期的なコストパフォーマンスを重視したい方におすすめです。
住宅のメンテナンス負担を抑える主な建材・工法とは?
ローコスト住宅で問題になりがちなメンテナンス費用は、建材・工法を変えることで解決できます。具体例を見ていきましょう。
外壁磁器タイル:塗り替え不要の高耐久性
外壁磁器タイルは紫外線や風雨に強く、素材自体の塗り替えは基本的に不要です。一般的なサイディングでは10〜15年ごとに、平均100万円以上の塗装費用がかかりますが、磁器タイルなら大幅な削減が期待できるでしょう。
システム瓦(乾式工法):メンテナンスフリーを実現
経年劣化しやすい漆喰やモルタルを使用しないシステム瓦(乾式工法)により、メンテナンスフリーな住まいを形にします。高気密・高断熱・遮音性に優れた住宅は、快適性を保ちながら光熱費を削減できるのが魅力です。
ローコストな注文住宅の弱点を補う?「RC(鉄筋コンクリート)住宅とは?
ローコスト住宅は初期費用を抑えられる反面、間取りの自由度や断熱・耐震性能、メンテナンス費用、資産価値などに不安が残るのが弱点です。
一方でRC(鉄筋コンクリート)住宅は、建物を支える主要構造体に鉄筋コンクリートを用いることで、以下のようにローコスト住宅特有の課題を解消しています。
- 耐震・耐火性が高い: 地震・火災・水害に強く、耐震等級2・3相当の性能を確保
- メンテナンス頻度が低い: 打ちっぱなしやタイル外壁で塗り替え周期を延ばせる
- 資産価値の維持しやすい: 建材などの劣化が遅く、市場評価が落ちにくい
RC住宅は、鉄筋とコンクリートの強度を活かした、耐久性と耐火性に優れた住まいです。重厚な構造のため地震の揺れに強く、津波や洪水などの大規模災害にも耐えられる高い安全性を備えています。
とりわけ茨城県南部のように、災害リスクの高い地域では、RC住宅の強みが大きな価値を持ちます。
柏市風早北部地域ふるさと協議会の配布資料によると、茨城県では今後30年以内に震度6弱以上の大地震が発生する確率が80%以上とされています。
こうした背景から、守谷市・つくばみらい市など、災害への備えが重要となるエリアにおいて、耐震性・耐火性に優れたRC住宅は有効な選択肢になるでしょう。
なお、大手ハウスメーカーのRC住宅は、ブランド料や広告費が上乗せされる分、総額が高くなりがちです。反対に地域密着型の工務店は、余分なコストを抑えつつ、高品質なRC住宅を適正価格で販売しています。
参考:柏市風早北部地域ふるさと協議会「茨城の地震の危険度は?30年以内に大地震が起こる確率は80%以上」
【Q&A形式】ローコストな注文住宅でよくある疑問

最後に、ローコスト住宅に関して、多くの方が抱く疑問とその回答をまとめました。
Q1: ローコスト住宅は本当に危険なの?
建築基準法は満たしているため、信頼できる業者を選べば基本的には問題はありません。ただし、建材や設備のグレードが抑えられている分、耐久性や断熱性が劣る可能性があります。
Q2: 後から後悔する人の特徴は?
建物本体価格だけで判断し、付帯工事や諸費用を含めた総額を把握していない人は後悔するかもしれません。結果的にオプション費用がかさんだり、断熱性能を軽視して光熱費が高くなったりするケースもあります。
Q3: 何年くらい住めるの?寿命は?
家の寿命は建材や施工の質、メンテナンス次第です。適切なメンテナンスを行えば30〜80年程度住み続けることも可能ですが、安価な建材の場合は劣化が早まる傾向にあります。
まとめ
ローコスト住宅は、初期費用を抑えてマイホームを実現できるのが大きな魅力です。その反面、間取りやデザインの自由度が限られる、メンテナンス費用がかさむ、資産価値が下がりやすいといったリスクをともないます。
茨城県南部のように地震や水害のリスクが高い地域では、耐震性・耐火性に優れたRC住宅など、将来の安心を見据えた選択を検討したいところです。自分や家族の暮らし方・将来のライフプランを考慮し、後悔のない家づくりを進めてください。
下記サイトでも住宅ローンの情報が掲載されていますので是非ご覧ください。
住宅ローンの事前審査期間が長い理由とは?長い場合の対処法を解説! – ローンとおるくん
社名:株式会社壁工房
本社所在地:〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹126-5
建設業者許可番号:茨城県知事許可-第035753号
つくばみらい工場
〒300-2346 茨城県つくばみらい市青木350-2
Tel 0297-21-7855 Fax 0297-44-5150